
連絡帳にどんな内容を書けばいいのか、毎日悩んでしまう…



例文があれば見たい。
この記事ではこのような悩みを解決できます。
連絡帳は情報を絞ってわかりやすく書くと、伝えたい内容が保護者に届きやすいです。また、保護者からの質問や相談に対して真摯な対応で返答することで、信頼関係が深まります。
書き方を間違うと、保護者の不信感を与えるほか、クレームに発展する可能性もあります。保護者と良好な関係を維持するためにも、正しい書き方を覚えましょう。
本記事では、保育士の方に向けて連絡帳の書き方を例文を交えて解説します。書くときのポイントや注意点も紹介しているので、参考にしてみてください。


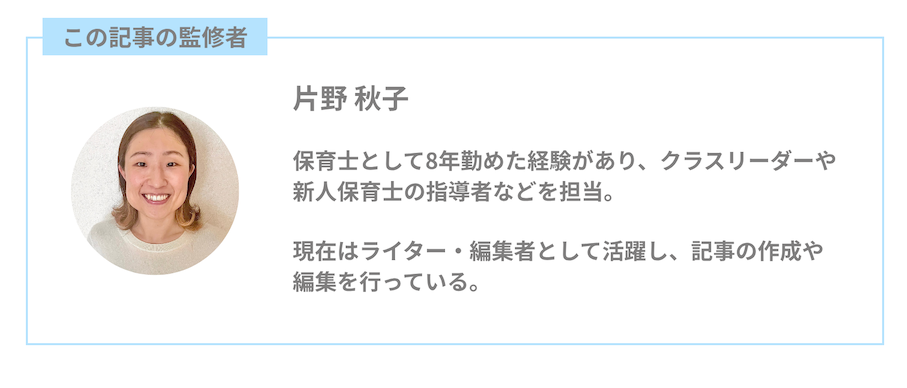
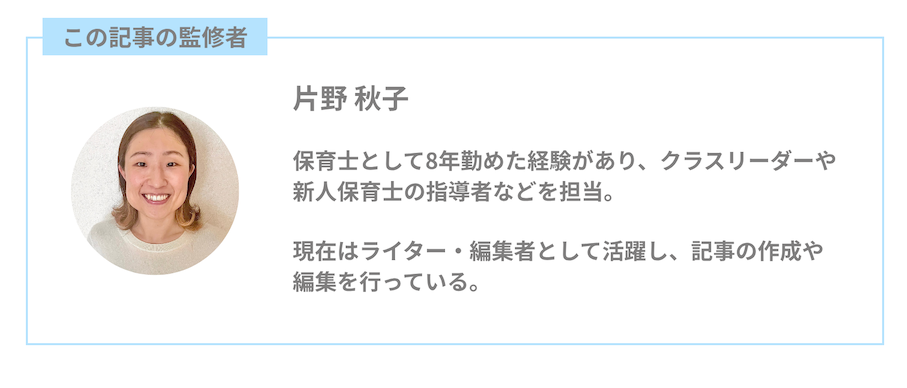
保育士が書く連絡帳の役割


連絡帳は、保護者との信頼関係を深める大事なツールです。そのほかにも連絡帳には大事な役割があります。
連絡帳の主な役割は以下の3つです。
- 子どもの健康状態を共有する
- 子どもの家庭での過ごし方や様子を知る
- 保護者の悩みや不安を把握し支援につなげる
役割を知ると、何を書けばよいかが明確になるため、連絡帳が書きやすくなります。
子どもの健康状態を共有する
連絡帳には、子どもの健康状態を共有するための項目が設けられているものが多いです。
代表的な項目と確認できる健康状態を以下の表にまとめました。
| 項目 | 確認できる健康状態 |
|---|---|
| 食事量 | 食欲の有無を把握できる。 食事量が減少していれば、お腹の不調や風邪の前兆などの体調不良の可能性が考えられる。 |
| 睡眠時間 | 寝不足・帰宅後の夕寝の状況を確認できる。 寝不足だと情緒の乱れや集中力低下につながる。 帰宅後に夕寝を多く取っている場合、夜眠れなくなり、生活リズムの乱れが心配される。 |
| 排便の状況 | 便の回数や状態により、便秘や体調不良の推測が立てられる。 |
| 朝の熱 | 平熱よりも高い場合、体調を崩す可能性を予測できる。 熱の高さによっては、子どもの安全を考えて、登園を控えてもらうよう保護者に相談する。 |
これらの健康情報を日々共有することで、子どもの体調の変化を早期に発見し、適切な対応につなげられます。
子どもの家庭での過ごし方や様子を知る
家庭から子どもについての情報を得ることは必要不可欠です。
- 今日は少し寝不足気味
- 家のトイレでおしっこができた
- 昨日家でたくさん叱ってしまった
など、家でどのように過ごしたのか、何があったのかを共有し、その情報を元に保育園での対応を考えます。
ちょっとしたことでも保育をするうえでのヒントになるので、情報はなるべく多くキャッチしておきましょう。



たとえば、いつもより子どもが元気がない日は、昨夜寝る時間が遅かったというケースは珍しくありません。
連絡帳の情報を活用すれば、普段より静かな遊びを提案したり、午睡時間を少し長めにしたりするなど、子どもの体調に合わせた柔軟な対応ができます。
保護者の悩みや不安を把握し支援につなげる
連絡帳には、保護者の育児に対する悩みや不安が書かれていることも多いです。
返信する際は、共感を示す言葉を使いながら、保育士の専門性を活かした具体的なアドバイスをすると保護者の不安が軽減します。
相談内容が深刻な場合は、連絡帳ではなく直接お話しする機会を設けましょう。書面では限られたスペースの中での回答になりますが、口頭であれば時間をとって話せます。
しんぷる保育では、保育に携わる方に向けたお役立ち情報を「しんぷる保育コラム」にて随時配信中です!保育中の悩みや就職・転職に関する情報を幅広く紹介しているので、気になる記事をチェックしてみてください。
保育士が連絡帳を書くときのポイント





連絡帳をうまく書くときのポイントを知りたい!
保育士は以下の5つのポイントを意識すると、読みやすく、保護者に伝わりやすい連絡帳になります。
- 丁寧に書く
- わかりやすくまとめる
- 保護者の質問や相談に返信する
- 子どもの様子を詳しく記載する
- 重要事項は口頭で伝える
少し意識を変えるだけで連絡帳を書くクオリティがグッとあがるので、実践してみてください。
丁寧に書く
連絡帳は丁寧に書く意識が大切です。その姿勢は保護者に伝わり「わが子をよく見てくれているんだ」と信頼関係の構築につながります。
字も綺麗に書くようにしましょう。読みにくい字は保護者にとって読む際にストレスを与えます。
また、乱雑な文字より、読みやすく整った文字のほうが信頼されやすいです。
わかりやすくまとめる
連絡帳を書く際は、内容をわかりやすくまとめる意識も持ちましょう。読みやすさに配慮しなければ、保護者に読む負担をかけてしまいます。
配慮する点は、たとえば1文の長さです。1文が長すぎると、内容が伝わりにくくなります。1文を簡潔にまとめるとすっきりとした文章に仕上がります。
【NG例(1文が長い)】
今日は◯◯公園に行って、◯◯ちゃんは、◯◯くんと手をつないで歩いて、歩いている途中にてんとう虫を見つけて「てんとう虫さん、かわいい!」とうれしそうにお話していました。
【OK例(1文が短い)】
今日は◯◯公園に散歩に行きました。◯◯ちゃんは、◯◯くんと一緒に手をつないで歩きました。
歩いている途中でてんとう虫を発見し、◯◯ちゃんは「てんとう虫さん、かわいい!」とうれしそうにお話していました。
また、情報を多く詰め込む書き方もわかりにくさを招きます。連絡帳はなるべく1つの情報を掘り下げて書いたほうがよいです。具体性が増すため、そのときの情景が浮かびやすくなります。
【NG例(情報量が多い)】
今日は◯◯公園に行って、みんなでかけっこをしました。かくれんぼもして◯◯ちゃんはとても楽しそうでした。すべり台には3回、ブランコは2回ほど乗りました。今日の給食はカレーで、完食しました。苦手なにんじんも頑張って食べてました。
【OK例(情報を厳選)】
今日は◯◯公園に散歩へ行きました。広場でみんなでかけっこや落ち葉拾いを楽しみました。
かけっこしていたとき、お友だちが転んでしまいました。◯◯ちゃんは転んだお友だちのもとにかけより「痛かった?大丈夫?」と言って、立つのを手伝ってあげていました。
お友だちは◯◯ちゃんの声かけに安心したのか笑顔になりました。◯◯ちゃんの優しさが垣間見える瞬間でした。
【OK例(情報を厳選)】
今日は◯◯公園に散歩へ行きました。広場でみんなでかけっこや落ち葉拾いを楽しみました。
かけっこしていたとき、お友だちが転んでしまいました。◯◯ちゃんは転んだお友だちのもとにかけより「痛かった?大丈夫?」と言って、立つのを手伝ってあげていました。
お友だちは◯◯ちゃんの声かけに安心したのか笑顔になりました。◯◯ちゃんの優しさが垣間見える瞬間でした。
連絡帳は、読む側の立場に立って配慮して書きましょう。
保護者の質問や相談に返信する
連絡帳に保護者からの質問や相談が書かれている場合は、返信します。真摯な回答を心がけると、信頼関係が深まります。
【例文】
保護者:
明日はお休みします
保育士:
ご連絡ありがとうございます。承知しました。
【例文】
保護者:
保育園では野菜を食べてますか?家だとあまり食べてくれなくて。
保育士:
園では、野菜を残す日もありますが、お友だちが食べている様子を見て「私も食べてみる!」と挑戦する姿がよく見られます。
家庭と園では環境が違うため、食べ方に差があるのは自然なことです。無理をせず、お子さんのペースを大切にしながら、野菜に親しむ機会を作っていただければと思います。
【例文】
保護者:
最近、子どものイヤイヤがすごくて悩んでます。子どもに怒ってしまう場面も多く、申し訳なく感じています。
保育士:
イヤイヤ期は成長の証でもありますが、毎日だと対応に困ってしまいますよね。
園でも同じような場面がありますが「◯◯したかったのね」と気持ちを受け取ると、気持ちを切り替えて次の行動に移れるときが多いです。
質問や相談に対して何も返信がないと、保護者は不安になったり、関心がないと感じたりしてしまいます。短くても構わないので、何らかの返信を必ずすることが大切です。



細かいニュアンスが書面で伝えられないと判断した場合は、直接伝える方法でも問題ありません。
口頭だと、保護者の表情や反応を見ながら話を進められるため、理解度を確認しながら伝えられます。
子どもの様子を詳しく記載する
子どもの様子はできるだけ詳しく記載してください。園で過ごす子どもの姿が目に浮かび、保護者の安心や喜びにつながります。
【NG例】
電車のおもちゃでたくさん遊びました。
【OK例】
今日は電車のおもちゃに夢中になって遊んでいました。積み木で踏切を作り「カンカンカン、電車が通ります!」と電車の運転手さんになりきっていました。
【NG例】
トイレでおしっこができました。
【OK例】
今日もトイレでおしっこができました。
最初は行くのを渋っていたのですが、お友だちがトイレに座っている様子を見て「座ってみる」と言ってトイレに座りました。座るとすぐにおしっこが出ました。
とても嬉しかったようで、周りにいる保育士に「トイレできたよ!」と笑顔で伝えていました。
【NG例】
給食を完食しました。
【OK例】
炊き込みご飯が気に入ったみたいで、口に入れるとおいしいと言って嬉しそうにモグモグ食べてあっという間に完食しました。
保護者はどんなに小さいことでも知りたいと思っているので、ちょっとした出来事でも積極的に報告しましょう。
重要事項は口頭で伝える
以下のような重要事項は連絡帳には書かず、口頭で伝えたほうがよいです。
- 園での体調不良の様子
- 期日が迫っている提出書類の催促
- 園内での怪我や友だちとのトラブル
体調不良は子どもの健康面を左右する大事な情報です。緊急性があるため、書面ではなく口頭で伝えましょう。
準備物や提出書類の催促に関しては、直接伝えたほうが保護者の理解度が高まります。必要に応じて連絡帳にも記載しておくとダブルの伝達で確実に対応してもらいやすいです。
怪我やトラブルに関しては、書き言葉だけでは微妙なニュアンスや背景が伝わりにくく、誤解を生む可能性があります。口頭で伝えると、保護者の表情やリアクションから不安や不信感を読み取れるため、その場でフォローできます。
ケース別|保育士の連絡帳の書き方【例文あり】


担当クラスや時期によって連絡帳の書き方は異なります。
ここでは、ケース別に保育士の連絡帳の書き方と例文を見ていきましょう。
- 0歳児
- 1〜2歳児
- 3歳児以上
- 年度初日
- 年度末
例文はアレンジして使ってみてください。
0歳児
0歳児は多くの子どもがまだ言葉を話せません。また、月齢が低い子は歩けないので、活動範囲がどうしても限られがちです。
そのため、小さなリアクションや表情の変化を連絡帳に書くと、子どもがどんなことに刺激を受けて、どんなことに興味を持ったのかが保護者に伝わります。
【例文】
日中は園庭に出て遊びました。シートを敷いてその上でゆっくり過ごしました。大きな葉っぱを渡してみると、握ったり、投げたりして葉っぱに触れる感覚を楽しんでいました。
近くにいたお友だちにも興味があるようで「あっ!」と言って、お友だちに触れて笑顔を見せる様子が見られました。
【例文】
今日は雨だったので室内で過ごしました。
音が出る玩具が気に入ったようで、繰り返しボタンを押して楽しんでいました。音が鳴るときは少し興奮気味になり、手足をバタバタ動かす姿がとても可愛らしかったです。
【例文】
今日の離乳食はにんじんのおろしだったのですが、口に入れた瞬間は渋った表情を見せていました。しかし味がわかると安心したようで、その後はパクパク口にして完食しました。
1〜2歳児
1〜2歳児は歩行ができるようになり、活動範囲が広がります。できることも増えていくため、連絡帳には日中の活動の様子や成長が感じられる様子を記載しましょう。
この時期は言語の発達が見られるものの、自分の気持ちをまだうまくは伝えられないため、内面の葛藤も連絡帳に書いてもよいです。
【例文】
今日は◯◯公園へ散歩に行きました。友だちが鉄棒にぶら下がる様子を見て◯◯ちゃんも挑戦!最初は1秒ほどで手が離れたのですが、繰り返して遊んでいるうちに5秒もぶら下がることができました。
「いっぱいできた!すごい?」と◯◯ちゃん自身がとても喜んでいました。
【例文】
今日は制作活動で絵の具を使ってあじさいを作りました。
◯◯くんは、手にたくさんの絵の具を付けて集中して取り組んでいました。赤色と青色の絵の具が混じり合う様子を見て「見て!色が違う!」と色の変化を楽しんでいました。
今日の給食に野菜スープが出ました。最初はにんじんを残していたのですが「にんじん食べたらおっきくなるよ!」と伝えると、頑張って食べ始めて完食しました。「ぜんぶ食べたよ!」ととても嬉しそうな◯◯くんでした。
【例文】
今日は室内でダンスしてたときに、◯◯ちゃんが浮かない表情をしていました。どうしたのかいくつか理由を聞いてみたのですが、首を振って違うと主張します。
そのとき、お友だちの◯◯ちゃんの姿をじっと見ている様子が見られたので「◯◯ちゃんが履いてるスカート(保育園の玩具用)を履きたいの?」と聞くと「うん!」頷きました。
隣のクラスに同じ玩具のスカートがあったので、一緒に取りに行くととても嬉しそうに身につけていました。その後は、お友だちと楽しそうにダンスを踊っていました。
3歳児以上
3歳児以上のクラスになると、連絡帳がなくなる保育園も多いです。言葉が発達して、その日の出来事や気持ちを自分の言葉で保護者に伝えられるようになるからです。
ただし、方針により連絡帳を継続する保育園や希望者だけ連絡帳を使用する保育園などさまざまなケースがあります。
3歳児以上は、言葉が発達して子どもたち同士でコミュニケーションを取れるようになります。ルールのある遊びも理解できるようになるため、意見の食い違いや競争心で衝突が起こりやすくなる時期です。
運動会や発表会などでは、目標や役割を持って参加するようになります。活動に取り組む中で、心の葛藤や成長も見られます。
連絡帳には日中の様子や挑戦する姿勢、感情の変化などを記録しましょう。
【例文】
今日は◯◯公園に遊びに行きました。◯◯くんはお友だちと鬼ごっこを楽しんでいました。途中から子どもたち同士で独自のルールを加えて、より楽しいゲームに発展させていました。
◯◯くんは「もっと〜〜したほうが面白いんじゃない?」と積極的に意見を発言していました。お友だちの意見を「それいいね!」と肯定する姿もあり、協調性も見られました。
【例文】
今日は発表会について話し合いがありました。
劇の演目をクラスのみんなで話し合ったのですが、◯◯ちゃんは「3匹のこぶたがいい!」と発言しました。3匹のこぶたの絵本が1・2歳児クラスにあったため、小さいクラスのお友だちが喜ぶのではないか?と思いやりのある提案をしてくれました。
今日で話し合いは終わらなかったので、明日も話し合いの続きを行う予定です。子ども同士で意見を出し合って決めていく過程を、温かく見守っていただけると嬉しいです。
年度初日
年度初日は、持ち上がりか、新しいクラスを担当するかによって書き方が変わります。
どちらの場合であっても、年度初日の連絡帳には、これから1年お世話になる保護者へ挨拶しましょう。
【例文(持ち上がりの場合)】
本年度も引き続き担任を務めさせていただきます。◯◯ちゃんの成長を間近で見守れることを大変うれしく思います。
今年度も保護者の皆さまと連携を取りながら、楽しく安心できる毎日をつくっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【例文(新しいクラスを担当する場合)】
0歳児クラスで◯◯組の担任を務めさせていただきます、◯◯です。
最初は新しいクラスに不安や戸惑いもあるかと思いますが、◯◯ちゃんが安心して過ごせるよう心を込めて関わっていきます。保護者の皆さまと一緒に成長を見守っていければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
【例文(新任保育士の場合)】
今年度より◯◯組を担当させていただきます、◯◯です。
まだまだ至らぬ点もあるかと思いますが、◯◯ちゃんの気持ちに寄り添いながら毎日を大切に過ごしていきたいと思っています。1年間どうぞよろしくお願いいたします。
年度末
年度末は1年間お世話になった感謝の気持ちを伝えましょう。持ち上がる場合、担任が変わる場合かによって伝える内容は異なります。
【例文(持ち上がる場合)】
この1年、◯◯くんご家族のご理解とご協力に支えられながら、◯◯くんとたくさんの思い出を作ることができました。本当にありがとうございました。
来年度も引き続き担任をさせていただきます。◯◯ちゃんの成長をまた一緒に見守らせていただけることを大変嬉しく思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
【例文(担任が変わる場合)】
1年間、本当にありがとうございました。◯◯ちゃんが日々成長する姿にたくさんの感動をもらいました。◯◯ちゃんのご家族とその成長を共有できたことにも感謝しております。
クラスは離れてしまいますが、引き続き◯◯ちゃんの園生活が実りあるものになりますよう近くで見守っていきます。



保護者からも感謝の言葉をいただく機会が多いので、お互いの気持ちを伝え合う大切な時間にしたいですね!
しんぷる保育では、保育に携わる方に向けたお役立ち情報を「しんぷる保育コラム」にて随時配信中です!保育中の悩みや就職・転職に関する情報を幅広く紹介しているので、気になる記事をチェックしてみてください。
【3パターン】連絡帳の書き出しから書き終わりまでの例文3つ





書き出しから書き終わりまでの例文が見たい!
ここでは以下3つのパターン別に連絡帳の書き出しから書き終わりまでの例文を紹介します。
- パターン1.子どもの様子をメインで伝える場合
- パターン2.保護者から相談があった場合
- パターン3.保護者にお願いがある場合
アレンジすれば、日々の連絡帳にも活用できるので参考にしてみてください。
パターン1.子どもの様子をメインで伝える場合
【保護者からのメッセージ】
保育園からの帰宅後、疲れたようで17:00〜18:00まで夕寝をしました。起きてからは少しグズグズでいつもよりも半分ほどしかご飯を食べませんでした。それ以外は変わらず元気です。
【例文】
夕寝から気持ちの切り替えが難しかったのかもしれませんね。園では特に変わりなく過ごせていました。
今日は、◯◯公園へお散歩に行きました。◯◯くんは、◯◯ちゃんと砂場で遊んでいました。カップに砂を入れ「お茶です、どーぞ」と◯◯ちゃんに渡していました。
2人でゴクゴク飲む真似をして「ぷはー!」と言っていて、とても可愛かったです。
パターン2.保護者から相談があった場合
【保護者からのメッセージ】
お風呂に入るのを嫌がります。おもちゃで遊び終わったら、お風呂入ると約束したので、遊び終わったタイミングで声をかけたら、泣いてお風呂を拒否しました。
ここ最近毎日こうで困っています。どうしたらいいのでしょうか?
【例文】
毎日同じような場面が続くと、おつらいですよね。
遊びやゆったり過ごすことの方が楽しくて、お風呂に入ることが少し億劫になっているのかもしれませんね。「今日のお風呂は◯◯を持って入ろうか!」など、ちょっとした楽しみを作ってみるのはいかがでしょうか?お風呂での特別な楽しみがあると気持ちの切り替えがスムーズにいくかもしれません。
また「絵本1冊読んだら入る?それとも2冊読んでからにする?」など、お子さんに選択肢を与えてあげると、自分で決めた気持ちになって動きやすくなることがあります。
パターン3.保護者にお願いがある場合
【保護者からのメッセージ】
帰宅後は、夢中でパズルをしていました!家にある24ピースのパズルは簡単にできるようになったので、さらに上のピースのパズルを買ってあげたいと思います。
食欲はあり、夕食をペロリと完食しました。
【例文】
最近、保育園でもよくパズルに集中して取り組んでいます。ちゃんと形を見て当てはめているので、パズルの仕組みをよく理解してきているようです。
今日は制作活動でてるてる坊主を作りました。折り紙でのちぎり絵なのですが、指先を使って細かく折り紙をちぎっていました。「女の子のてるてる坊主」といって、ピンク色の折り紙を選んでいました。
※明日は雨予報のため、レインコートを着て園庭で活動をする予定です。以前よりお願いしておりましたレインコートを、忘れずにご準備いただけると助かります。
保育士が連絡帳を書くときの注意点


連絡帳は書き方を間違えると保護者の信頼関係を損なう可能性があります。
良好な関係を維持するためにも、以下3つの注意点に気をつけながら書いてみてください。
- ケガやトラブルなどは直接伝える
- ネガティブな内容は書かない
- 大事な用件は上司に伝える
順番に解説します。
ケガやトラブルなどは直接伝える
子どもがケガをしてしまった、友達とトラブルがあったなどの場合は、降園時あるいは電話で、必ずその日のうちに直接伝えるようにしましょう。
連絡帳にも書いて伝えたいことを整理しつつ、直接伝えるのでもよいです。事の大小に関わらず、保育園で起きたことはすべて保育園側の責任です。誠意を持って謝罪し、今後の対応を考える必要があります。
ただし、友達とケンカをしてそのあと仲直りができたエピソード、成長を感じられた出来事などは連絡帳に書いても問題ありません。
ネガティブな内容は書かない
子どもが問題行動を起こしたり、言うことを聞かなかったりするなどのマイナスな部分は、連絡帳に書くことは避けましょう。
ネガティブな出来事を文字だけで伝えようとすると、誤解を招きトラブルの原因になりやすいためです。伝達が必要だと思う内容は直接口で伝えるようにします。
大事な用件は上司に伝える
以下のように、保護者のコメントで大事な用件だと判断した場合は、上司に伝えたほうが良いです。
- ◯◯ちゃんに叩かれたと家で言っている
- 汚れ物の服があまりにも泥だらけで洗うのが大変だった
- 最近、家で癇癪が激しく、親がノイローゼ気味になっている
- お迎え時間について融通を利かせてもらえないかという相談
内容によっては、のちほど苦情やトラブルに発展するリスクがあります。
上司に伝えておくとタイミングを見て保護者に声をかけたり、謝罪の言葉を伝えたりできるため、トラブルを回避しやすいです。
また、保護者の不満や要望の声は、園で改善すべき課題かもしれません。
上司に報告することで、保育内容や環境を見直すきっかけとなり、園全体の改善につながる場合もあります。
連絡帳の書き方のコツを覚えて保育士と保護者の信頼関係を深めよう


連絡帳は書き方のコツを知ると、書きやすくなります。ポイントをおさえたわかりやすい文章をベースにすればよいため、悩んで連絡帳を書く手が止まることもなくなるでしょう。
本記事で紹介した例文や注意点も参考にしながら、日々の連絡帳作成に活用してみてください。
しんぷる保育では、保育に携わる方に向けたお役立ち情報を「しんぷる保育コラム」にて随時配信中です!保育中の悩みや就職・転職に関する情報を幅広く紹介しているので、気になる記事をチェックしてみてください。
また、就職・転職をご検討中の方も「しんぷる保育」にご相談ください。
弊社は1都3県の東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、保育士の就職・転職サポートをおこなっている地域特化型の転職エージェントです。


関東のほぼすべての保育園と取引しているため、豊富な求人の中からあなたの希望に合う保育園を厳選してご紹介いたします。
無料で利用できるので、まずは登録してどんな求人があるかチェックしてみてください。
\ たった30秒で登録完了 /

