
保育士の仕事で大変なことって?



エピソードもあれば知りたい
このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
保育士は「給料が低い」「休憩がない」「残業が多い」など、大変な仕事のイメージが付きやすい職業です。実際に、待遇面や職場環境への不満から離職する保育士も少なくありません。
本記事では、保育士の仕事で大変なこと10選をエピソード付きで解説します。
大変だと感じることは、職場環境の改善や転職で解決できるケースも多くあります。
自身で変えられることは改善して、あなたの理想の働き方を見つけましょう。


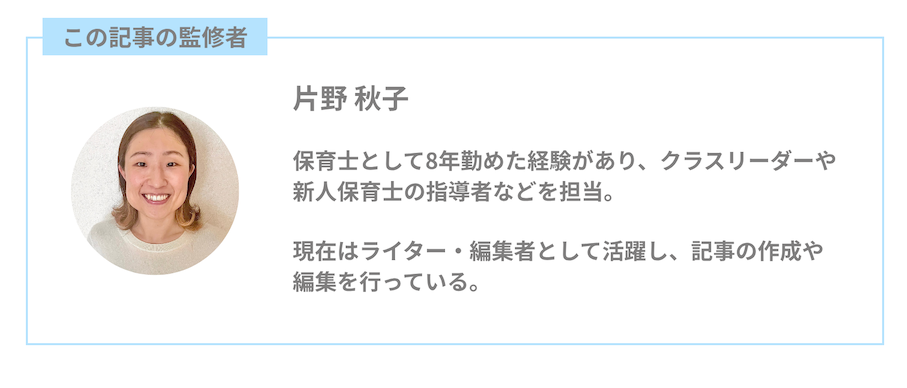
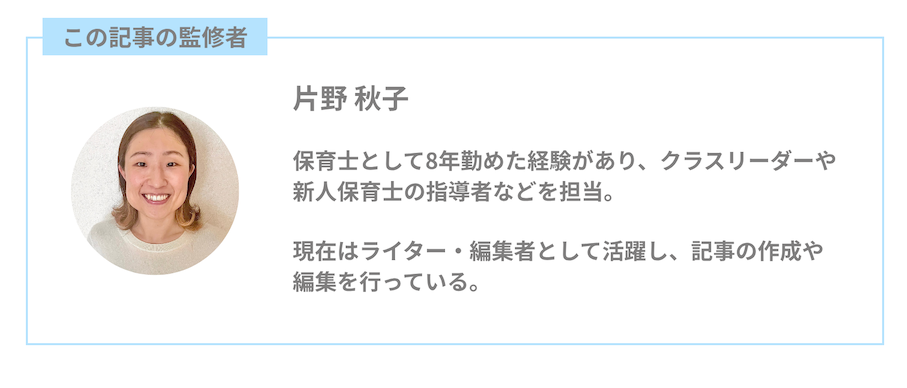
保育士の仕事で大変なこと10選【エピソード付き】


さっそく、保育士の仕事で大変なことを見ていきましょう。保育士が苦労したり、悩んだりしやすい内容を10個紹介します。
- 給与が安い
- 労働時間が長く、残業になりやすい
- 持ち帰り残業が多い
- 業務内容が多い
- 休憩時間がとれない
- 保育方針が合わない
- 体力がもたない
- 人間関係に苦労することが多い
- 仕事のプレッシャーを感じやすい
- 休日が取りにくい
エピソードも交えて解説するので、あわせてご覧ください。
給与が安い
厚生労働省が実施した「平成28年賃金構造基本統計調査」によると、保育士の平均年収は約327万円です。
政府が実施する処遇改善の取り組み効果により、保育士の給料は上昇傾向にあります。
しかし、地域や経験年数、各園の処遇改善の取り組み具合に応じて保育士の給料に差が生じます。条件次第では手取りの月収が15万円に届かないケースも珍しくありません。
保育士の仕事は、子どもの命を預かる責任のある仕事です。仕事の責任や負担と給料が見合っていないと考える保育士は多いです。
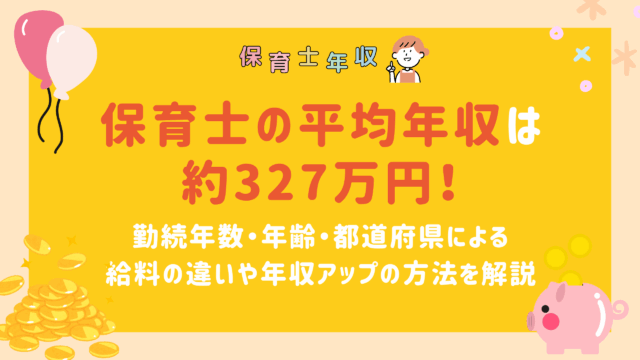
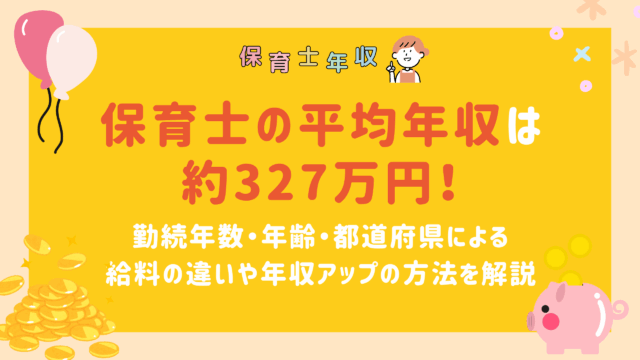



地方で働く友人の保育士から聞いた話ですが、新卒の頃は手取りが12万円ほどだったそうです。
地域によって給与水準が大きく異なることを実感しました。
給料を上げるには、役職手当を受けられるキャリアアップ研修の受講や平均給料の高い地域や園へ転職する方法があります。
以下の記事では、全国で保育士の給料が1位である東京都の給料について徹底解説しています。転職を検討する際の参考にしてみてください。


労働時間が長く、残業になりやすい
保育士は子どもの保育活動を終えたあとに、夕方から園内清掃や事務作業を始める場合が多く、残業になりやすい職業です。
また、人員不足で最低限の職員数でまかなっている園も残業になりやすいです。一人ひとりが抱える業務量が増え、勤務時間内に仕事を終わらせることが難しいからです。



遅い時間まで残業する保育園で働いていたことがあります。慢性的な疲労感を覚え、転職を考えるきっかけにもなりました。


持ち帰り残業が多い
保育士は業務量が多く、業務を持ち帰って行う「持ち帰り残業」が常態化している保育園もあります。
主に保育指導計画書、園だより・クラスだより、行事の計画案などを持ち帰って作成し、保育士はプライベートの時間を削って仕事をしなくてはなりません。
労働環境を改善すべく厚生労働省が行動を起こしていますが、まだまだ環境整備ができていない園もあります。
ただ、状況を改善しようと残業をなくすために取り組む園や、スキマ時間や休憩時間を活用している園も増えているようです。
業務が終わらなくて困っている場合は、上司や先輩に相談して負担を減らす工夫をしましょう。
業務内容が多い
保育士は業務内容が多く、保育士が不足している園では必要最低限の人数で業務を行っているのが現状です。そのため、業務負担の多さも原因で退職している保育士の方も多くいます。
厚生労働省の資料によると、令和4年における保育士の求人倍率は、2.04倍となっていて、9割を超える都道府県で1倍を超えています。つまり、全国的に保育士不足に陥っているのです。
早朝から閉園時間まで、子どもの保育時間では常に動き回り、子どもがいない時間の業務では量が多いことから、長時間労働になることが多々あります。
また、多忙のあまり余裕がなくなりストレスを抱え、子どもにあたってしまい、不適切保育につながってしまう事例もあります。


休憩時間がとれない
一般的な企業では、仕事の合間やお昼に休憩時間がありますが、保育士は子どものお昼ご飯の補助する必要があるため、子どもから目を離せません。
そのため、休憩をとる時間がなかなか取れない職業だといわれています。
仕事中にリラックスする時間がないため、疲れが顔に出てしまったり、集中力が続かなかったりと、疲れがたまり、心身ともに辛い保育士さんもいるかもしれません。
保育士さんの中には、園内清掃をゆとりをもって行い、身体を休める時間にしたり、子どものバスの送迎を終えた後に、園に帰るまでのバスで休憩したりと、一日の仕事の中で、休憩を意識してとっている方がいるようです。
経営者の方の中には「保育士は休憩時間がないのが当たり前」と考える方もいるかもしれませんが、保育士の方が体調を崩さないためにも、休憩時間を確保する取り組みが必要だと思われます。



休憩がほとんどない保育園で働いていたことがあります。
その後、休憩をしっかり確保する保育園に転職し「体制がきちんと整ってさえいれば休憩はしっかり確保できるんだ」と思いました。


保育方針が合わない
保育施設は園の保育方針が決められており「パソコンや英語、音楽活動などのカリキュラムが組まれている園」や「外遊びが多く、のびのびと子どもを保育する環境の園」など、園によってさまざまです。
新人の頃は毎日の保育活動を一生懸命に励んでいて疑問に思わないかもしれませんが、働いている中で、徐々に自分の保育観が徐々に確立される方もいるかもしれません。
そういった方は保育をしていて、大切にしたいものや思いが大きくなり、園長や上司と園の保育方針でぶつかる場合もあるかもしれません。
働いている園のカラーや保育方針が合わないと感じたら、自分の保育観に合った保育施設へ、転職を検討してみるのも一つの手です。


体力がもたない
保育活動中に子どもの相手をして走ったり、園内の清掃したりと体力が必要な活動がたくさんあります。
若いうちは何とか気力で乗り切れても、年齢を重ねるごとに体力が続かず、体調が悪くなる場合もあるかもしれません。
休憩時間が確保できる業界と異なり、保育士の仕事は変則的に対応する必要があるため、しっかりと休憩する時間が取れない職業と言われています。
保育士は製作活動や事務作業などが多いですが、保育士の仕事は体力が問われるので、身体を壊してしまわないように、自分の身体をメンテナンスする時間を作るなどして、持続的に保育士として働くために自分の体を気にしてみてください。
休憩時間がなかなか取れない園もあるかもしれませんが、働きやすい環境を整えるためにも園長や上司と相談して、問題点を改善していきましょう。
人間関係に苦労することが多い
どんな業界でも人間関係で悩む人はたくさんいます。
保育士の仕事は、子どもと関わるだけではなく、出勤して退勤するまで一日中、同じ職場で職員達と顔を合わせながらコミュニケーションを取る必要があります。
一般的に女性が多い保育施設では派閥やグループが生まれてしまうことがあり、人間関係に悩む保育士の方がたくさんいます。保育士2年目の退職理由の約40%が、人間関係を理由に退職しているほどです。
小規模の保育施設の場合は、複数人で担任を持つ場合をはじめ、一緒に働く同僚・上司との相性がとても大切です。
折り合いの悪い場合は、職場の雰囲気が合わずにつらい思いをすることもあるかもしれません。
まずは良質な人間関係を作り上げるために、同僚や上司と積極的にコミュニケーションをとり、話をよく聞く姿勢を忘れないようにすることが大切です。
職場のチームワークを育むためにも互いのいいところに目を向け、挨拶や感謝の気持ちを素直に表現することから始めるなどして、職員間の信頼関係を築き上げることができると良いですね。


仕事のプレッシャーを感じやすい
保育士は、保護者から大切な子どもを預かるとても大きな責任をともなう仕事です。
常に子どもの安全や、健康状態を常に気にかけていく必要があります。
園児を散歩に連れて行く時、車や自転車、バイクや歩行者など、さまざまな危険から子どもたちを守っていかなければなりません。
ケガや事故が起きないよう、職員間でマニュアルを作成するなどの対策をとってください。
わからないことや不安なことがあった場合は、保育士の先輩や上司に相談して対策案などを一緒に考えてみましょう。



プレッシャーを感じやすい性格だったので、精神的に辛くなることも多かったです。
一人で抱え込まず、チームで協力することを意識すると気持ちが少し楽になりました。
休日が取りにくい
最近では、さまざまな働き方に対応するために、遅い時間帯まで延長保育を実施する園や年中無休で預かりを実施している園などもあります。
勤務先の園によっては、土日祝日に出勤しなければならない園もあるでしょう。
さらに、勤務先の園が人員不足の場合は、なかなか休みが取りにくいことも考えられます。
病欠や有休が取りにくい場合は、働きづらさを感じることもあるかもしれないので、別の園に転職を考えても良いかもしれません。
【年齢別】保育士が苦労や悩みを感じやすいポイント





子どもたちの年齢によっても保育士の大変さって変わってくるの?
結論、子どもたちの年齢ごとに大変さの種類や内容は異なります。ここでは、以下3つの年齢グループに分け、それぞれで苦労や悩みを感じやすいポイントを紹介します。
- 0歳児
- 1〜2歳児
- 3〜5歳児
順番に見ていきましょう。
0歳児
0歳児は、成長の速度に個人差が大きく、一人ひとりに合わせた対応に大変さを感じやすい年齢です。
例えば、ずりばいやハイハイの子もいれば、歩き始めている子もいます。
保育士は個人の発達段階に合わせて活動や環境設定を工夫しなければなりません。
また、離乳食の段階も個々によって違い、子どもの咀嚼力や発達状況に応じたサポートが必要です。
さらに、0歳児は誤飲や転倒などの事故が起こりやすい年齢です。
誤飲も転倒も1歩間違えると命に関わる重大な事故につながります。そのため、常に緊張感を保たなければならず、保育士は神経をすり減らしやすいです。



はじめて0歳児の担任になったとき、個別対応の大変さに驚いた記憶があります。
しかし、「はじめてのつかまり立ち」や「はじめてのハイハイ」といった、成長に立ち会う場面も多く、たくさんのやりがいもありました。
1〜2歳児
1〜2歳児は、身体面や言語面の発達が著しく進み、散歩へ行ったり、友達同士で遊んだりし始める年齢です。
自我の芽生えとともにイヤイヤ期に突入する年代でもあり、対応に戸惑う保育士も少なくありません。
特に新人の保育士は子どもが泣いたり、怒ったりする理由をうまく察することができず、信頼関係の構築に悩みやすいです。
また、子どもの予測できない行動が増えるため、保育者同士の連携がより大切になります。
相性の悪い方とペアを組んだり、報連相(報告・連絡・相談)が苦手な保育士がいると、業務に支障が出やすく大変です。
3〜5歳児
3〜5歳児は、体力が付き活動量が増える年齢です。
言語面や社会性の発達も進み、友だちと話し合ってルールを決めたり、役割のある遊びをしたりします。
身の回りの自立に向け、個々への細かな配慮が必要です。例えば、食後の歯磨きや荷物の整理整頓など、一人ひとりの状況を把握したうえでサポートしなくてはなりません。
また、幼児になると保育士の数が減り、4・5歳クラスの場合、1クラスで最大25人の子どもを一人で受け持ちます。
身の回りのことは自立してきているとはいえ「子どもと丁寧に関われない」「手のかかる子どももいて一人担任では大変」といった理由で、負担を感じる方もいます。
保育士がやりがいを感じるとき


大変なことを経験しつつも、やりがいを持って働く保育士は多いです。ここでは保育士が感じる代表的なやりがいを3つ紹介します。
- 子どもの成長を感じられる
- イベント行事を成功させたとき
- 園児の卒園を見送ったとき
それぞれ詳しく解説します。
子どもの成長を感じられる
保育士の仕事での一番の魅力は、子どもの成長が見られたときに感じられます。
前までは嫌いだった野菜を食べられるようになったり、落ち着いて物事に取り組める時間が長くなったりなど、子どもの成長の瞬間に立ち会えるのは、子どもが好きな保育士の方にとっては嬉しいことだと思われます。
イベント行事を成功させたとき
職員の方々や、子どもと協力して大きなイベントを成し遂げたときにはやりがいを感じられるようです。
年中行事の中でも大きなイベントである、クリスマス会や運動会などを、職員みんなで成功させたり、トラブルを共に乗り越えることで信頼感が生まれ、仕事にやりがいを感じられます。
園児の卒園を見送ったとき
卒園児を共に担当した先生同士であれば、卒園まで一緒に保育した子どもたちを、送り出せたことに大きな達成感を味わえるでしょう。
保育士さんは小さかった子どもたちが大きく成長する瞬間に立ち会えるやりがいのある職業と言えます。
以下の記事では、保育士のやりがいを全部で7つ紹介しています。保育士のやりがいをさらに知りたい方は、参考にしてみてください。


働きやすい職場を探したいなら「しんぷる保育」にご相談ください



給料が高い保育園で働きたい



休憩がしっかり確保されている保育園を探している



残業ゼロの意識が高い保育園に就職・転職したい
このようにお考えなら『しんぷる保育』にご相談ください。
しんぷる保育は1都3県の東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、保育士の就職・転職サポートをおこなっている人材紹介会社です。


しんぷる保育は関東のほぼすべての保育園と取引しているため、豊富な求人の中からあなたの理想の保育園を厳選してご紹介いたします。
「今の職場よりも年収アップを実現できる保育園を探してほしい」
「一人暮らしをする予定なので家賃手当が高い保育園を紹介してほしい」
「有給休暇の取得率が高い保育園を見つけてほしい」
といったご要望にも対応いたします。
無料で利用できるので、まずは登録してどんな求人があるかチェックしてみてください。
\ たった30秒で登録完了 /
保育士の大変なことでよくある質問


最後に保育士の大変なことでよくある質問と回答をまとめます。
面接で保育士の仕事で大変なことを聞かれたときなんと答えれば良いですか?
あなたが感じた大変なことを正直に伝えても構いません。そのときに「どうやってその大変なことを乗り越えたのか」も一緒に伝えましょう。
ただ大変なことを伝えるだけでは、ネガティブな印象に聞こえます。しかし、大変さを乗り越えた経験を伝えると、あなたの成長や問題解決能力が評価されます。
以下は回答の例文です。
大変に感じたことは、初めて2歳児クラスの担任を任されたときに、子どもから試し行動を取られ、信頼関係がなかなか築けなかったことです。
私がオムツ交換しようとすると「◯◯先生はイヤ!違う先生がいい!」と言われ、オムツ交換を拒絶される日が続きました。
同じクラスの先輩保育士に相談したところ「今は注意の声掛けが多くなっているから、A君とゆっくり遊ぶ時間を作ってみたら?」とアドバイスをいただきました。
いただいたアドバイスのとおり、次の日からA君と遊ぶ時間・話す時間を意識的に増やしました。
すると、少しずつ心を許してもらい、A君のほうから私と一緒にトイレに行くと言ってくれたのです。
このときの大変な経験を通して、子どもとの信頼関係の大切さや、先輩に相談することの重要性を学びました。
なお、大変なことに「給料が低くて生活が大変だった」「人間関係が悪かった」といった内容は避けましょう。
転職しても職場環境に対して不満を言う印象を持たれやすいです。


保育士の大変なことランキングを知りたい
ここでは大変なことの順位付けを、厚生労働省が公表している保育士の離職理由で割合が多い順に示します。
結果は以下のとおりです。
| ランキング | 大変なことの具体例 |
|---|---|
| 1位:職場の人間関係 | ・同じクラスの担任と仲が悪い ・高圧的な上司や先輩に指導を受ける ・後輩が指示を聞かず業務に支障が出る ・派閥があり職場の雰囲気が悪い |
| 2位:給料が安い | ・手取りが低く生活が苦しい ・責任の重さに対して給料が見合わない ・昇給額が少なく将来が不安 ・ボーナスが少ないまたは出ない |
| 3位:仕事量が多い | ・仕事量が多く毎日残業になる ・書類作成や製作物を持ち帰って作業する ・行事の準備で休日出勤がある ・保育以外の雑務が多い |
| 4位:労働時間が長い | ・毎日残業で疲労感が蓄積する ・休憩なしで働き続ける日が多い ・シフトが不規則で生活リズムが崩れる ・持ち帰り仕事で自宅でも休めない |
| 5位:妊娠・出産 | ・妊娠して体力的に仕事を続けるのが難しい ・保育園側の妊娠中に対する配慮が不十分 ・子育てと保育士の仕事の両立ができない |
参考:過去に保育士として就業した者が退職した理由|厚生労働省
人間関係や待遇面での不満が上位を占めており、これらの問題が改善されることで、保育士の離職率軽減が期待されます。
保育士の大変なことに対する改善策を見つけていこう!


職場環境によって、保育士が感じる大変さの度合いは大きく異なります。例えば、給料に満足できる保育園に就職・転職した場合、給料の低さに悩みません。
また「残業なし」を徹底している保育園や休憩をしっかり確保している保育園に入社すれば、ストレスや疲れを感じにくくなります。
「保育士は大変な職業」とひとくくりにせず、職場環境の改善に向けて行動しましょう。



今の職場では改善が見込めなそう…
このような状況であれば、転職を検討するのも一つの方法です。
働きやすい環境の保育園を見つけることで、保育士としてのやりがいをより感じられます。
1都3県への就職・転職をご希望の方は『しんぷる保育』にご相談ください。関東のほぼすべての保育園と取引しているため、あなたの希望に合った求人を厳選してご紹介できます。
無料で利用できるので、まずは登録してお気軽にご相談ください。
\東京・埼玉・神奈川・千葉に転職なら /

