
保育園見学では何を質問すればいいの?」



どんな質問をすれば、自分に合った職場かどうかを判断できるの?
このような疑問をもつ方もいるのではないでしょうか?
保育園見学は、あなたが長く働ける環境かどうかを見極める貴重な機会です。
適切な質問をすれば、園の保育方針や職場環境など、求人情報だけではわからない実態を把握できます。しかし、何を質問すれば良いのか悩む方も多いでしょう。
本記事では、保育士として保育園見学で聞くべき質問リスト25選をご紹介します。質問の意図や聞き方のコツ、避けるべき質問なども解説しているので、参考にしてみてください。


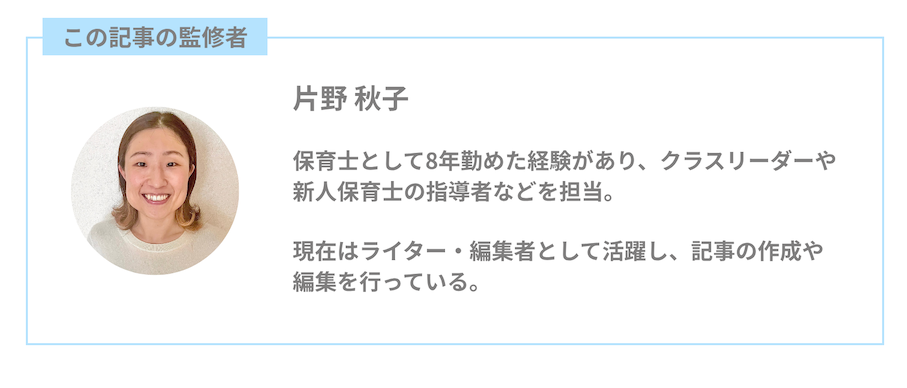
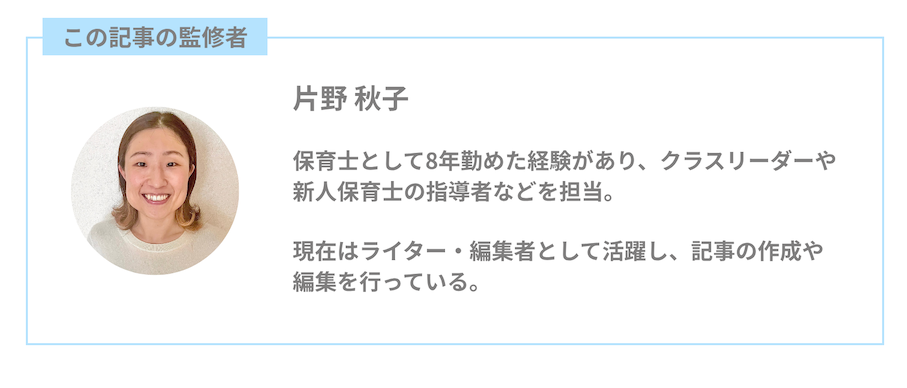
【保育士向け】保育園見学での質問リスト


保育園見学で確認しておきたい質問を項目ごとにリストにしてまとめていきます。
- 保育内容・方針に関する質問
- 園行事・保護者対応に関する質問
- 給食・食事に関する質問
- 健康・安全管理に関する質問
- 職場環境・労働条件に関する質問
それぞれ質問の意図と、質問してわかることを参考にしてみてください。
保育内容・方針に関する質問
保育に対する考え方が合うかどうかは、あなたのやりがいや働きやすさに直結します。以下の質問で園の方針とマッチするか確認しましょう。
1.園ではどのような保育を重視していますか?また、特別な教育はありますか?
この質問で自分の保育観と園の方針が合うかどうかを見極められます。
園が「自然との触れ合いを大切にしている」「子どもの主体性を育む環境づくりに力を入れている」など、どのような考え方や活動を重視しているかを確認できます。
リトミック、英語、体操など特別な教育に力を入れている場合、自分の得意分野を活かせるかどうかもわかります。
2.具体的な保育スケジュールについて教えてください
この質問で実際の業務の流れや時間配分がわかり、自分のペースや働き方と合うかをチェックできます。
また、子どもの生活リズムをどれだけ大切にしている園なのかも判断できます。
3.お散歩で行く場所は?頻度はどのくらいですか?
子どもは室内で過ごすだけでなく、外で体を動かしたり、自然と触れ合ったりする経験も大切です。質問を通して、園外保育の実施状況をチェックしましょう。
散歩の距離感からは、子どもが散歩に慣れているかがわかります。
散歩に同行する保育士の数も聞いておくと、安全性への配慮も確認できます。



わたしは、散歩に同行する保育士の数の確認を大切にしてました。
特に乳児クラスの散歩の場合は、歩行が安定していないほか、注意力も散漫で危険性が高いです。
そのため、職員の同行数が配慮されているかどうかは事前にチェックしていました。
4.慣らし保育の期間と進め方はどのようにされていますか?
この質問で新入園児への配慮姿勢や保育士の負担がどの程度かを把握できます。
特に0歳児クラスの慣らし保育は大変です。どれくらいの期間を設けるのか、どういうスタンスで慣らし保育をするのかを知ることで、子どものペースを大切にする園かどうかがわかります。
慣らし保育を大切にしている園では、子どもが落ち着きやすく、対応する保育士の負担も軽減されます。
5.トイレトレーニングや歯磨きのしつけはいつから始めますか?
この質問で生活習慣の自立に関する園の方針がわかります。
園によって指導の開始時期や取り組み方がさまざまです。
園でしっかり対応するのか、家庭に指導をお願いする方針なのかで、業務内容や保護者対応の仕方も変わってきます。
園行事・保護者対応に関する質問
仕事とプライベートのバランスを考える上で重要な、園の行事・保護者対応についての質問をまとめました。
6.イベントの回数や開催曜日を教えていただけますか?
この質問で行事準備の負担度がわかります。
イベントの回数が多いと、そのぶん準備や練習に時間を要します。また開催曜日によっては休日出勤の可能性もあるため、ワークライフバランスを考える上で重要な情報です。
7.保護者懇談会はありますか?
この質問で保護者対応の頻度や方法、園の保護者との関わり方がわかります。
懇談会がある場合、開催する曜日(休日)や時間帯(勤務後)などの情報も得られ、休日出勤や時間外勤務の可能性を推測できます。
懇談会の進め方や雰囲気(カジュアルか、形式的か)も聞くと、保護者とのコミュニケーションスタイルがわかります。
給食・食事に関する質問
子どもの食育や安全について、具体的な対応方法をチェックできる質問内容をまとめました。
8.食物アレルギー対応は具体的にどうされていますか?
この質問で園の安全管理体制の徹底度がわかります。
アレルギー対応は命に関わるので、対応がしっかりしている保育園かどうか見極めましょう。
調理師から給食を受け取る際のやりとり、複数担任でのダブルチェック体制、食事提供中の注意点、万一アレルギー反応が出た場合の対応方法などの具体的な安全対策方法が見えてきます。



回答があいまいな保育園は、安全意識が低い可能性があるため、入社の判断は慎重に検討しましょう。
9.離乳食の段階はどう設定されていますか?
この質問で乳児の食事への配慮と安全対策の水準がわかります。
離乳食の対応次第で誤飲の事故につながるケースもあります。
段階をしっかり設定している保育園は安全性を大切にしている証拠です。また、個々の発達に合わせた対応をしているかもチェックできます。
10.おやつはどんなものが出ますか?
この質問でおやつに関連する業務内容や園の食育への姿勢がわかります。
例えば、おやつが市販のものか手作りかで、園の食育に対する取り組み方が判断できます。
また子どもにおやつを提供する場合、保育士がどこまで準備するかを聞いておくと業務負担の程度が把握できるでしょう。
園によって、おやつの盛り付けを調理師・保育士のどちらが担当するかという対応の違いがあります。



わたしは調理師さんの給食やおやつを食べることが好きだったので、手作りのおやつを提供する保育園には自然と惹かれました。
11.職員の給食はどのような取り方をされていますか?
この質問で給食時間の過ごし方や福利厚生の一面がわかります。
子どもと一緒に食べるのか、別の場所で食べるのかで、休憩時間の過ごし方が全く違います。
また給食費についても聞いておけると良いでしょう。園によっては、園が給食費を全額もしくは一部負担してくれる場合もあります。
また、お弁当の持参が認められているかどうかも確認しておくとよいでしょう。食費を節約したい場合に、お弁当の持参を選択できます。
健康・安全管理に関する質問
保育園での安全管理や、子どもの健康に関する質問リストをまとめました。
12.午睡時のチェックはどのようにされていますか?
この質問でSIDS(乳幼児突然死症候群)対策の具体的方法と安全管理の徹底度がわかります。
乳児はSIDS(乳幼児突然死症候群)の危険があるため、午睡チェックの方法は重要です。
保育園での午睡チェックは、内閣府が策定した「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」に基づき、全国の保育施設で実施されています。
何分ごとにチェックしているのか、午睡チェックの専用機器を使用しているかなど、安全管理の方法や徹底度がわかります。
13.怪我や体調不良による呼び出しにはどのような基準がありますか?
この質問で体調不良時の対応基準と保護者連絡の方針がわかります。
例えば、熱が37.5度を超えた時点で必ず連絡する場合、少し様子を見てから連絡する場合など対応の仕方や基準は園によって異なります。
また、呼び出し対応をするのは看護師に限られているのか、保育士も担当するのかなどルールの違いも把握できます。保育士も担当する場合は、対応業務が増えることになります。



呼び出し対応は原則看護師さんが担当していた保育園で働いていたことがあります。
連絡するために保育を抜けなくて済むため、看護師と保育士の業務の切り分けができている職場に働きやすさを感じました。
14.保育園を休まなければならない基準をおしえてください
この質問で感染症対策や体調管理の方針がわかります。
咳・鼻水がひどい場合の登園可否や、体調回復の判断基準など、各園で対応が異なります。
子どもの健康管理への姿勢や感染症対策の徹底度がわかるとともに、保護者対応の厳しさも推測できる重要な情報です。
15.保育園での飲み薬や塗り薬の対応方法は?
この質問で与薬の管理体制と安全対策がわかります。対応できるのは原則看護師ですが、ルール決めがしっかりしているかどうかの判断材料になります。
明確なルールがあるかどうかも、安心して働ける指標になるでしょう。
16.看護師さんは在籍していますか?また、不在時はどう対応していますか?
この質問で医療的ケアの体制と緊急時対応の準備状況がわかります。
看護師の在籍状況と、不在時の対応方法がしっかり決められているかは重要なポイントです。
対応方法が曖昧だと、医療的な対応が必要な場合にトラブルになる危険性があります。
なお、保育所(認可保育園)において、看護師の設置は「義務」ではなく、「努力義務」とされています。
参考:厚生労働省|児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
17.おむつの処理方法はどのようにされていますか?
この質問で衛生管理と日常業務の一部がわかります。
おむつの処理方法は、主に園で処理する場合と家庭に返す場合の2パターンです。
園で処理する場合は溜まったオムツを捨てる作業、家庭に返却する場合は各児童のビニール袋に使用済みオムツを入れる作業が発生します。
後者の方が、個別対応が増え、手間がかかることが多いです。
職場環境・労働条件に関する質問
勤務する保育園の職場環境・労働条件について、自然にチェックできる質問リストをまとめました。
18.クラスの担任の数はどれくらいですか?
この質問で人員配置の余裕度と一人当たりの業務負担がわかります。
配置基準ギリギリの職員か、それとも配置基準+αの職員を雇っているのかで、保育士一人当たりの負担は大きく異なります。
人員に余裕がある園では、事務作業や行事の準備に専念できる時間を確保しやすいです。休憩も取りやすいため、働きやすさの重要な指標になります。



非正規社員を積極的に採用して、人数にゆとりのある保育園で働いたことがあります。
子どもとゆっくりと関われるほか、乳児クラスは大人の目が増えることで安全性も向上しました。
19.職員同士の関係性や雰囲気はどうですか?
この質問で職場の人間関係や組織文化を知ることができます。
実際に見学して感じ取れる部分もありますが、質問することで園側の認識や人間関係の構築に関する取り組みがわかります。
人間関係が良好な職場かどうかは、長く働き続けるために非常に重要です。


20.休憩の取り方や休憩場所はどうなっていますか?
この質問で労働環境の適切さと職員の健康への配慮がわかります。
法律で定められた休憩時間がしっかり確保されているか、保育から離れて心身ともに休める環境で休憩できるのかをチェックできます。
休憩時間の確保は当たり前のことですが、実際には守られていない園も存在するため、外せないチェックポイントです。


21.書類の量や作成頻度を教えてください
この質問で事務作業の負担度と業務効率化の取り組みがわかります。
日誌、週案、月案、個別記録などの書類作成負担がどの程度あるかわかります。雛形を見せてもらえると、記入するボリュームもチェックできます。
保育DX(デジタル化)推進により、電子保存や申請の簡素化が進み、ICTやアプリを導入して作業負担の軽減を図っている園も増えているので、システム化の状況も確認すると良いでしょう。
参考:こども家庭庁|保育DXの推進について
22.保育園の装飾(壁画や手作りの置物など)はありますか?誰が担当するのですか?
この質問で業務外の負担度と園の保育環境への考え方がわかります。
最近は保育士の負担軽減や、家庭的な温かい環境を大切にする観点から、装飾を最小限にする園も増えています。
装飾担当が固定されているか、全員で分担するかによっても負担は変わります。
23.連絡は紙媒体ですか?それともアプリなどを使用されていますか?
この質問で事務作業の効率性とICT化の進み具合がわかります。
連絡手段によって作業負担に大きな違いが出てきます。
電子対応に慣れていれば、アプリのほうが記録作業の負担は少なくなりますし、記録の管理や検索も容易になります。



業務効率化を進めるため、ICT化に積極的な保育園も多いです。
働きやすさを大切にしたい方は、ICT化の状況も確認しておくとよいでしょう。
24.職員会議の様子を教えてください
この質問で会議頻度と時間管理の姿勢がわかります。
会議の回数(多いか少ないか)、時間帯(休日、昼休憩、勤務後など)、会議の雰囲気(効率的か、長時間に及ぶか)がわかります。
会議の持ち方は園の組織文化を反映することが多く、働きやすさの重要な指標となります。
25.ピアノを演奏する機会はありますか?
この質問で特定スキルの必要性と個人の特性への配慮度がわかります。
ピアノが苦手な人にとっては重要なポイントです。
ピアノ演奏が必須なのか、苦手な保育士への配慮(代替手段や担当の調整など)があるのかがわかります。自分のスキルと業務のミスマッチを事前に防ぐことができます。
保育園の見学中にわかることがあるかもしれませんが、もし不明点があれば質問してしっかりと確認しておきましょう。
保育園の見学で確認すべきポイント


保育園の見学をなんとなく周りを見渡すだけで終わらせてしまっては、見学の意味がなくなってしまいます。
あとになって、聞いておけばよかったとならないよう、事前に確認しておきたい不明点や疑問点をリストアップしましょう。
子ども達の様子
保育園で遊んでいる子どもたちが、のびのびと楽しそうに過ごせているかを確認しましょう。
元気に怪我なく遊んでいる姿は、衛生環境が整えられていることが確認でき、給食をしっかり食べていることがわかります。
子どもたちの表情からも、さまざまなことが読み取れます。わが子がここで遊ぶ姿をイメージしながら、子ども達の様子を確認しておきましょう。
保育士の様子
保育士さんが生き生きと楽しそうに働いていらっしゃるかを確認しましょう。
感受性の強い子どもたちは言葉を吸収していき、成長に大きく影響します。強い言葉やショックな出来事によってPTSD(心的外傷後ストレス障害)に陥りやすいです。
保育士の声のトーンや言葉づかいにもそういった予兆がみられると思うのでチェックしましょう。
もし保育士がふだんとは明らかに異なることをしていれば、子どもの顔に表れます。
また、保育園は子どもの年齢と人数に応じて、定められた人数の保育士を配置しなければなりません。実際の様子を確認して、人数バランスが安心できるものか確認するといいでしょう。


設備の状態
子供にとって安心して過ごせる環境か、遊戯室には子どもが怪我をしないように工夫がされているか、掃除は行き届いているか、保育園そのものの状態なども確認しておきましょう。
1日の流れを想像して、子どもに危険がないかをシミュレーションすることも確認方法の1つです。
また、子どもの送り迎えを考えて、駐輪場・駐車場の広さや、周りの道路なども確認しておきましょう。
保育園見学の前にするべき3つの準備





保育園見学の当日までに何を準備したらいい?
保育園見学を成功させるためには、事前の準備が重要です。
- 見学する園のリストアップ
- 見学申し込みの連絡【電話・メール】
- 当日の持ち物と服装のチェック
順番に見ていきましょう。
1.見学する園のリストアップ
まずは、見学したい保育園をリストアップしましょう。下記に条件をまとめました。
- 保育時間・通勤方法をチェックする場合→自宅から通える園はどこが近いか。
- 受け入れ可能な子どもの年齢をチェックする場合→チェックした園の預けられる年齢・月齢はいつからか。
- 開園する時間をチェックする場合→通常の保育時間、延長保育の時間は、何時から何時までか。
求人情報や保育士専門の転職サイト、口コミサイトなどを活用して、あなたの希望条件に合う保育園を探してみてください。
\東京・埼玉・神奈川・千葉に転職なら /


2.見学申し込みの連絡【電話・メール】
保育園が決まったら、次に見学の申し込みをします。申し込み方法は園によって異なるので、事前に調べておきましょう。
保育園見学の申し込み方法は、主に以下の3つです。
- 電話での申し込み
- メールでの申し込み
- Webでの申し込み
多くの園では電話での申し込みが一般的ですが、最近はWebフォームやメールで受け付ける園も増えています。
保育園は日中、子どもたちの保育で忙しいため、電話で申し込む場合は以下の時間帯を避けて連絡するのがマナーです。
- 朝の登園時間(7:00〜9:00)
- 昼食・午睡の時間(11:30〜15:00)
- 夕方の降園時間(16:00〜18:00)
電話をかけるなら、10:00〜11:00頃や14:00〜15:30頃がおすすめです。
また、卒・入園式シーズンや運動会・発表会の行事、年度替わりなどの繁忙期を避けて見学申し込みをしましょう。
3.当日の持ち物と服装のチェック
見学当日に備えて、持ち物と服装を整えます。保育園見学時の基本的な持ち物は以下のとおりです。
- A4サイズの資料が入るバッグ
- クリアファイル
- メモ帳・筆記用具
- 質問リスト
- スリッパ(園によっては持参)
- ハンカチ・ティッシュ
- マスク
これ以外にも園から指定された持ち物があれば、忘れずに準備しましょう。
保育園見学の服装は、清潔感があり、動きやすいかどうかが選ぶ基準です。基本はビジネススーツまたはオフィスカジュアルが適しています。
オフィスカジュアルとは、以下のようなカジュアルすぎない清潔感のある服装を指します。
- シャツやブラウス
- チノパンやひざ丈スカート
- ローファーやパンプスなど動きやすい靴
ジーンズやTシャツ、サンダルなどのカジュアルすぎる服装は、保育園見学には適さないため避けましょう。


保育園見学での効果的な質問テクニック


保育園見学では、ただ質問するだけでなく、どのように質問するかも重要です。
ここでは、保育園見学で実践したい4つの質問テクニックを紹介します。
- 質問は簡潔明瞭にする
- 謙虚で丁寧なコミュニケーションを心がける
- 理由や背景を添えて質問する
- 保育園見学でメモをとる
効果的な質問ができれば、より深い情報を得られ、園側からも好印象を持ってもらえるでしょう。
質問は簡潔明瞭にする
保育園の見学中の質問は、簡単でわかりやすい質問にすることを心がけましょう。
見学していて新たに不明点が増えてしまった、質問リストを用意していても、確認が漏れてしまったことなどもあるでしょうが、保育士の方々は子どもたちのお世話などでお忙しい中、説明をしてくれたり質問に答えてくれたりしています。
園の子どもたちや保育士の方、場合によっては一緒に見学をしている方の迷惑にならないように、前もって質問の要点をまとめておくと良いですね。
謙虚で丁寧なコミュニケーションを心がける
保育園見学では、謙虚で丁寧な姿勢で質問することが大切です。
園側は忙しい業務の合間に時間を割いて見学を受け入れてくれています。
「お忙しい中、見学の機会をいただきありがとうございます」という感謝の気持ちを忘れずに、以下のような丁寧な言葉遣いを心がけましょう。
- 「差し支えなければ、〜について教えていただけますでしょうか」
- 「もしよろしければ、〜についてお聞かせください」
- 「恐れ入りますが、〜について確認させていただきたいのですが」
謙虚な姿勢で質問することは、あなた自身の人柄やコミュニケーション能力のアピールにもつながります。
理由や背景を添えて質問する
単に「どうですか?」と聞くよりも、なぜその質問をするかの理由や背景を添えると、より具体的で的確な回答を得られます。
| 単純な質問 | 理由や背景を添えた質問 |
|---|---|
| 「行事はたくさんありますか?」 | 「子どもたちの成長につながる行事を大切にしたいと思っています。年間でどのような行事があり、準備はどのように進めているか教えていただけますか?」 |
| 「どんな保育をしていますか?」 | 「子どもの主体性を大切にした保育に興味があります。日常の保育で、どのような場面で子どもたちの主体性を育む工夫をされているか教えていただけますか?」 |
| 「研修はありますか?」 | 「保育士として常にスキルアップしていきたいと考えています。こちらの園では、職員の成長をサポートする研修制度や勉強会などがあれば教えていただけますか?」 |
「理由・背景」+「質問内容」の順番で質問すると、自身の保育に対する考え方や価値観を伝えられる上、相手も答えやすくなります。
保育園見学でメモをとる
質問リストを作成して質問する準備を万端にしたところで、保育園見学当日に質問する際に一番大切なことがあります。保育園見学では必ずメモを取るようにしましょう。
保育園見学では、想像以上に多くの情報を得ることになります。メモを取らずにいると、以下のような問題が起こる可能性があります。
- 質問への回答内容があいまいになってしまう
- 複数の園を見学した場合、どの園の情報か混同してしまう
- 重要な情報を忘れてしまい、後で思い出せなくなる
簡潔に要点をまとめたメモがあれば、後で園を比較する際にも役立ちます。また、熱心に質問してメモを取る姿は、園側にも好印象を与えます。
\東京・埼玉・神奈川・千葉に転職なら /
保育園見学で避けるべき質問


「保育園見学ではどんな質問をしてもいいの?聞かない方がいいことってある?」
質問をすることは大切ですが、以下のような質問をすると、マイナスの印象を与えてしまう可能性があります。
- 公式サイトや資料に掲載されている質問
- 給料や待遇面の質問
- 他園と比較するような質問
見学時に避けるべき質問もあることを把握しておきましょう。
公式サイトや資料に掲載されている質問
見学の前に、必ず保育園のホームページをチェックして、事前に調べれば分かる内容について質問するのは避けましょう。
保育園の公式サイトや求人情報、パンフレットなどに掲載されているような「開園時間」「園児の定員数」といった基本情報を質問すると、準備不足と見られる可能性があります。
事前に調べた情報をもとに、より深掘りした質問をしましょう。
給料や待遇面の質問
初回の見学では、給料や福利厚生について直接的に質問するのは避けた方が良いでしょう。
給料や残業代、有給休暇の取得などの質問は、園側に「待遇面にしか興味がない」という印象を与えてしまいかねません。
給与や待遇面の詳細は、見学よりも求人票の確認や、採用担当者との個別面談で聞く方が適切です。






他園と比較するような質問
他の保育園と比較するような質問は、園側に不快感を与える可能性があるため避けましょう。
以下のような質問は、園に対する評価や批判をしているように受け取られかねません。
- 「〇〇保育園では〜をしていましたが、こちらではいかがですか?」
- 「近くの保育園より園庭が狭いように見えますが、外遊びはどうしていますか?」
- 「他の園では保護者参加の行事が多いですが、こちらはあまりないのですか?」
他園との違いを知りたい場合は比較ではなく、その園の特徴や力を入れている取り組みについて質問しましょう。
保育士として働く保育園の見学先をお探しなら「しんぷる保育」にご相談ください



保育園見学をしたいけど、どの園を選べばいいか分からない…



現職と両立しながら見学の約束を取るのが大変…
このようにお考えなら『しんぷる保育』にご相談ください。
しんぷる保育は1都3県の東京・神奈川・千葉・埼玉を中心に、保育士の就職・転職サポートをおこなっている地域特化型の転職エージェントです。
しんぷる保育は関東のほぼすべての保育園と取引しているため、豊富な求人の中からあなたの希望に合う保育園を厳選してご紹介いたします。園見学の日時や持ち物の確認といった園との連絡のやりとりは、弊社が代行いたします。
園見学する保育園を絞る際に、
「子どもとじっくり関わる保育を大切にしている園を紹介してほしい」
「残業が少なく、ワークライフバランスを重視している保育園を探している」
「研修制度が充実していて、キャリアアップできる環境が欲しい」
といったご要望もお気軽にお聞かせください。
無料で利用できるので、まずは登録してどんな求人があるかチェックしてみてください。
\ たった30秒で登録完了 /
保育園見学の質問リストについてのよくある質問


最後に保育園見学の質問リストに関するよくある質問と回答をまとめます。
保育園見学はいつから始めたがいいですか?
保育園見学は基本的に、1年中受け付けています。
4月に入園する予定の場合、遅くとも9月から10月頃までに見学を終えている方が多いため、早めのスタートが理想です。
転職の場合は、転職希望時期の3ヵ月前くらいから見学を始めるのがおすすめです。退職から入職までの期間を考慮して、余裕をもったスケジュールを立てましょう。
早い時期から複数の園を見学しておけば、自分に合った保育園を見つけやすくなります。
就活の際の見学や面接で質問したほうが良い内容はありますか?
新卒で就活する方は、教育体制の確認をしておきましょう。教育体制が整っていれば、安心してスキルアップしていけます。
具体的には、先輩保育士のサポート体制や、悩んだり困ったりしたときに、どのような相談体制があるかなどを質問してみてください。
職場環境や働き方の詳細においては、本記事で紹介した質問リストを活用すれば、効果的に情報収集できます。
保育園の見学で質問した方がいいことはありますか?
保育園見学では、園の特色や保育方針について質問するといいでしょう。
園側から「何か聞きたいことはありますか?」と逆質問される場合もあります。
その際は、園の方針や取り組みに対して肯定的な姿勢で質問すると好印象です。


インターホンでの挨拶の仕方は?
保育園見学時のインターホンでの挨拶は、第一印象を左右する大切なポイントです。以下のような流れで丁寧に対応しましょう。
- あいさつ・自己紹介:「おはようございます。保育園見学でお約束をいただいております、〇〇と申します」
- 用件:「本日〇時からお時間をいただいております」
- 感謝:「お忙しい中お時間をいただき、ありがとうございます」
インターホンで話す際には、ハッキリと聞き取りやすい声で丁寧に話しましょう。
保育園見学では保育士として働く目線で質問リストをまとめよう


保育園見学は、長く働ける理想の職場を見つけるための重要なステップです。
実際に保育園に見学に行くのと、パンフレット・ホームページで見るのとでは全く違います。
本記事で紹介した25の質問リストを参考に、あなたの働き方や価値観に合った質問項目を整理してみてください。
「質問リストを作ったけど、どの保育園を見学すべきか迷っている」
「自分の希望に合った保育園を効率的に見つけたい」
という方は、保育士向けの就職・転職支援サービス『しんぷる保育』にご相談ください。
しんぷる保育は関東のほぼすべての保育園と取引しています。あなたのご希望にあった求人を厳選し、理想の職場探しをサポートいたします。
無料で相談できるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
\東京・埼玉・神奈川・千葉に転職なら /


