
自由保育とはどんな保育方法?



一斉保育とはどのような違いがある?
このような疑問をおもちの方もいるのではないでしょうか?
自由保育とは、子どもの自主性を尊重し、一人ひとりが主体的に遊びを選択できる保育方法です。
保育士が活動内容を決める一斉保育とは異なり、子どもたち自身が興味や関心に基づいて自由に活動を選べるため、個性や創造性を育みやすいとされています。
一方で「集団行動が身につかないので はないか」「やりたい放題でクラスがまとまらないのではないか」などの懸念の声もあります。自由保育の効果を最大化に引き出すには、保育士の配慮的な関わりと環境設定が不可欠です。
本記事では、自由保育の特徴や一斉保育との違いについて詳しく解説します。それぞれのメリット・デメリットや、自由保育で気をつけるべきポイントも紹介しているので参考にしてみてください。


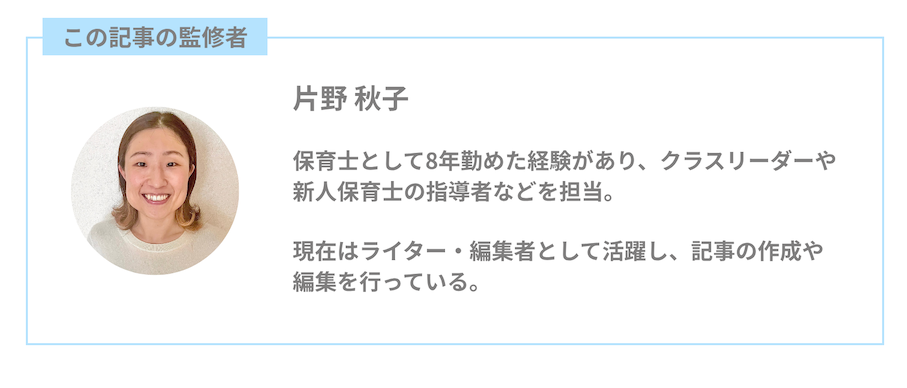
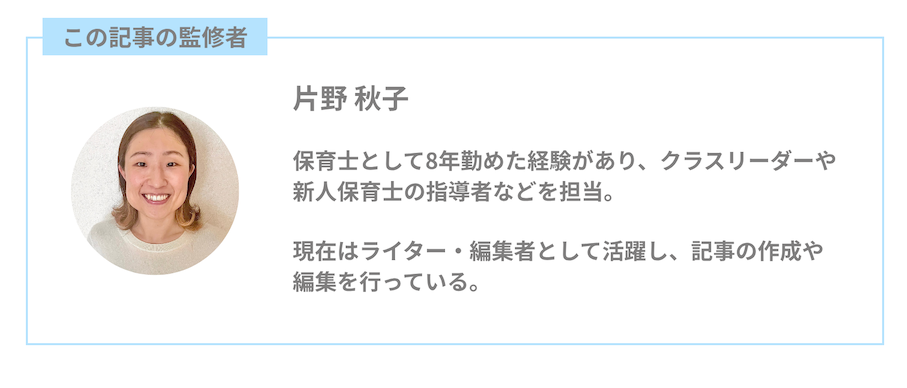
自由保育とは|子どもの自主性を尊重し主体的に遊びを選択できる保育


自由保育は、子どもたちが自分で考え、自由に遊べる保育環境です。
保育士は子どもの興味や関心を引く遊びを用意し、自由の中にも学びを得る要素を提供します。
具体的には、子どもが好きな玩具を自由に手に取れる環境を整えます。また、おままごとコーナーや積み木コーナーなどを常設して、いつでも好きな遊びを選択できるようにします。
子どもから「〇〇が作りたい!」と要望があった際に、すぐに対応できるよう準備や体制を整えておく保育士の柔軟性も自由保育では大切です。
このような環境と保育士の関わりにより、子どもは自分らしさを発揮しながら成長します。
自由保育の歴史は古く、大正時代にさかのぼります。
当時、東京女子師範学校附属幼稚園主事だった倉橋惣三が、児童中心の保育を提唱したところが自由保育のはじまりです。
子どもの自主性を育む保育方法として、現在でも多くの保育園や幼稚園で取り入れられています。
1日のスケジュール例
自由保育における1日のスケジュール例を紹介します。
今回は乳児クラスの1日の流れを紹介しています。幼児クラスでは遊ぶ時間が伸びたり、給食の時間が後ろに設定されたりするなど、タイムスケジュールが多少異なりますが、基本的な流れは変わりません。
| 時間 | 活動内容 |
|---|---|
| 7:00~9:30 | 順次登園・自由遊び |
| 9:30~10:00 | おやつ |
| 10:00~11:30 | 自由遊び(室内・戸外) |
| 11:30〜12:30 | 昼食 |
| 12:30〜15:00 | 午睡 |
| 15:00〜15:30 | おやつ |
| 15:30〜16:30 | 自由遊び |
| 16:30〜18:00 | 順次降園 |
このように、自由遊びの時間を多く取り入れながら、生活のリズムも大切にしたスケジュールとなっています。
自由保育と一斉保育(設定保育)の違い
自由保育と一斉保育では、子どもたちの活動内容やペースにおいて、以下のような違いがあります。
| 項目 | 自由保育 | 一斉保育(設定保育) |
|---|---|---|
| 活動の決定 | 子ども自身が選択 | 保育士が設定 |
| 活動内容 | 子どもの興味・関心に基づく | 全員で同じ活動 |
| 活動ペース | 子ども一人ひとりのペース | 集団で統一されたペース |
| 重視する要素 | 自主性・創造性・個性 | 協調性・ルール・規則 |
自由保育は興味や関心など子どもの個にスポットを当てるのに対し、一斉保育はルールや協調性など、集団での学びを重視します。伸ばす力や特徴が異なるものの、どちらの保育も子どもの成長に必要な要素を含んでいます。
両者は対照的なアプローチなので、どちらの保育方法を選ぶべきかで悩む方も少なくありません。
悩む方は、自由保育と一斉保育を組み合わせた「折衷型」の保育園を選択肢に入れてみると良いでしょう。
折衷型では、朝の会や制作活動などで一斉保育を取り入れながら、バランスよく保育を実践しています。



私は折衷型の保育園で働いていました。制作活動のときは一斉保育でそのほかの時間は子どもたちが好きな遊びを選べる環境でした。
個人的にはバランスが良く、働きやすかったです。
以下の記事では、保育園の種類を一覧で紹介しています。自由保育は保育園だけでなく、認定こども園や小規模保育園でも導入されています。保育園以外の施設に興味がある方は、参考にしてみてください。


自由保育の5つのメリット
自由保育を取り入れると、以下の5つのメリットがあります。
- 自主性を養える
- 創造力を育てられる
- 子どもの好きなことに気づきやすい
- 集中力を鍛えられる
- 柔軟な保育ができる
順番に解説します。
自主性を養える
子どもたちにとって、自由な遊びや学習の機会は非常に重要です。
自由な環境では、子どもたちは自分の興味や関心に基づいた活動に取り組む自主性を育めます。これにより、子どもたちの自己表現や自己肯定感が高まります。
自主性を発揮すれば、彼らの自己決定力も養われます。自分の好きな遊びを選択できるため、自分自身を表現する貴重な機会を得られます。自由な環境での活動は、子どもたちの成長において重要な要素です。
創造力を育てられる
自由保育では、子どもたちは、自分のアイデアや感情を表現する方法を見つけられ、創造的な表現力が育まれます。
自由な遊びの中で子どもたちは自分の興味や好みに基づいて活動できます。このような環境では、子どもたちは自分自身の創造力を発揮する機会が増えます。
たとえば、子どもたちは自分の好きな遊びや興味のあるテーマに取り組むことで、自分自身のアイデアを考え出し、それを実現するための方法を見つけだそうとします。
このような経験を通じて、子どもたちの創造的な表現力が育まれます。
子どもの好きなことに気づきやすい
自由保育では、保育士が子どもの興味や関心をより直接的に感じられるメリットがあります。
決められた科目をこなすのではなく、子どもたちが自由に遊ぶ姿を見守ることで、それぞれの興味や関心をより深く理解できます。
遊具やお友達との遊びなど、通園しないとできない遊びもあります。子どもにとって楽しいと思える場を提供できるのが、自由保育の一番のメリットです。
集中力を鍛えられる
子どもは、一つの物事に集中するのが苦手です。
決められたことに取り組みはじめても、すぐに注意がほかのものに向いてしまい、同じ行動を長く続けられません。
しかし、自由保育では、子どもが好きなことを自由にさせるのが基本方針です。その結果、子どもは遊びに集中しやすくなるので、結果的に集中力が鍛えられます。
柔軟な保育ができる
自由保育のメリットとして保育を柔軟におこなえることが挙げられます。
自由保育では毎年季節ごとのカリキュラムが決まっておらず、その年に合わせた柔軟な保育をおこなう園も多くあります。保育者は子どもたちの興味や関心に柔軟に対応し、保育プログラムを計画できます。
このような保育スタイルでは、子どもたちも積極的にカリキュラムに参加しやすくなり、その結果、大きな成長を遂げます。
しんぷる保育では自由保育を実施している保育園を探すお手伝いをいたします。無料で利用できるので、登録して求人をチェックしてみてください。
\東京・埼玉・神奈川・千葉に転職なら /
自由保育の4つのデメリット
自由保育にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットも存在します。
- 放任になる可能性がある
- 子どもの行動が偏りやすくなる
- 保育が難航する場合がある
- 人手が必要になる
下記では、それぞれのデメリットについて解説します。
放任になる可能性がある
自由保育のデメリットとして、子どもたちを自由にさせた結果、事故や喧嘩などといったトラブルが発生しやすいです。
自由保育と放任は全く別物ですが、自由保育の延長線上に放任があるため、そこの境界線がはっきりできていない園もあります。
自由保育であっても社会性や協調性を学ぶ場面や学ぶ必要はあるため、どこまで自由にさせているのか入園前に調べておく必要があります。
子どもの行動が偏りやすくなる
子どもが苦手なことや嫌いなことを避けやすいのも、自由保育のデメリットです。
文字の読み書きや基礎的な運動など、小学校以降で必要とされる要素を身に付けずに卒園してしまう可能性もあります。
小学校に入学後、同級生ができるのに自分の子どもができないことがあるのは、保護者にとって懸念材料です。
自由保育では、どこまで子どもの自主性を重んじるかの判断も大切です。
保育が難航する場合がある
自由保育は、子どもたちが自分の興味や関心に基づいて遊びや学びを選ぶ保育スタイルであるため、保育士の指導や管理が難しくなることがあります。
子どもたちは自分のペースで活動するため、集団での進行や時間管理が難しくなることも少なくありません。保育士は、子どもたちの個々のニーズに合わせたサポートを提供し、適切な誘導をおこなう必要があります。
また、自由保育では子どもたちが自己表現や自己主張をする機会が増えるため、衝突やトラブルが起こりやすくなることもあります。



新人の頃は子どもの要望や個々の行動にうまく応えられずよく苦戦していました。
自由保育は、柔軟性や対応力が特に必要だと感じています。
人手が必要になる
自由保育では、子どもたちがそれぞれの遊びや学びを選択するため、保育士の数は一斉保育より多く必要になります。
また、子どもたちの安全を確保するためにも、保育士が常に目を光らせる必要があります。そのため、人手が不足すると安全管理が難しくなります。
保育士は人手不足が続いているので、保育士の待遇をよくするといった対応が必要になってきます。


一斉保育の5つのメリット
一斉保育と自由保育の違いが理解できたかと思います。次に、一斉保育のメリットについて5つ紹介します。
- 平等に経験を積める
- 指導しやすい
- 小学校になじみやすい
- 集団生活のスキルが身に付けられる
- 成長レベルを把握しやすい
順番に見ていきましょう。
平等に経験を積める
一斉保育は、全ての子どもが平等に保育を受け、経験を積むことができます。
個別の指導ではなく、集団での保育を通じて社会性やコミュニケーション能力を身につけられます。一斉保育では、子ども同士が刺激し合いながら成長できるため、自己表現や自己主張の大切さを学べます。
一斉保育のような集団保育では、他の子どもたちと関わりながら協力や助け合いの経験もできます。
指導しやすい
一斉保育は、同じ年齢の子どもたちが一緒に過ごすため、指導しやすいといったメリットもあります。
子どもたちは、同じ年齢の子どもたちが一緒に遊ぶため、お互いに刺激を与え合い、ともに成長します。保育士は、子どもたちが1つの目標に向かうサポートをするため指導しやすいと言えます。
一斉保育では、グループでの活動が中心となるため、指導者が多くの子どもたちに対応できます。これにより、子どもたち一人ひとりに十分な関心や指導を行うことができ、個々の成長をサポートできます。
一斉保育は、子どもたちの社会性やコミュニケーション能力の発達に役立つだけでなく、指導者の効率的な指導も可能にする教育方法です。
小学校になじみやすい
一斉保育は、複数の子どもたちが一つのグループで集団生活をすることです。
この経験により、子どもたちは社会性や協調性を身につけられます。
たとえば、お友達と一緒に遊んだり、お互いに協力して活動したりすることで、他者との関わり方やコミュニケーション能力が向上するため、小学校になじみやすくなります。
集団生活のスキルが身に付けられる
一斉保育では、複数の子どもたちが一つのグループで一緒に過ごすことになります。
この環境では、集団生活のスキルを身に付けられます。一緒に遊んだり、話したりすることで、自分の意見を伝えたり、相手の意見を聞いたりする力が備わります。また、グループでの活動やルールを守ることも重要です。
一斉保育では、みんなが同じルールを守ることで、円滑な活動ができるようになります。そのため、協調性やルールを守る意識を養えます。
成長レベルを把握しやすい
一斉保育では、同じ年齢の子どもたちが一緒に過ごすことで、成長レベルを把握しやすくなります。
たとえば、同じクラスの子どもたちが共通の行動に参加することで、年齢に応じた発達の進み具合を比較できます。また、保育士が一斉に子どもたちを見守ることで、個々の成長を見逃すことが少なくなります。
そのため、保育士は子どもたちの様子を常に把握し、必要なサポートや指導をおこなえます。
一斉保育の3つのデメリット
一斉保育はメリットの他にデメリットも存在します。ここでは、一斉保育のデメリットについて3つ紹介します。
- 個性を育てにくい
- 自主性を育てにくい
- 柔軟性を育てにくい
以下では、それぞれのデメリットについて解説します。
個性を育てにくい
一斉保育では、子どもたちが集団で同じ活動や教材に取り組むため、個々の子どもの個性や特性を伸ばすことが難しくなります。
ある子が特定の教材に興味を持っているのに、他の子は全く興味を示さない場合、一斉保育ではその子の興味や関心に合わせたサポートが思うようにできません。
また、一斉保育では子どもたちが同じペースで進められるため、発達の遅れや進み具合の差が目立ちにくくなります。そのため、適切なサポートが行き届かない場合もあります。
自主性を育てにくい
一斉保育は、複数の子どもを一つのグループでまとめて保育するため、この形式では、個々の子どもの自主性を育てることが難しいと言われています。
これは、集団での活動や指示に従うことが求められるため、自分の意見や選択を自由に表現する機会が少ないことが挙げられます。
柔軟性を育てにくい
一斉保育のデメリットとして、柔軟性が育たない点があります。
一斉保育は集団での活動が中心であり、同じテーマや内容に基づいて進行するため、個々の子どもたちの個性や発達段階に合わせたカスタマイズが難しい側面があります。
子どもたち一人ひとりの興味やニーズに十分に応えることが難しく、柔軟なアプローチが限定される可能性があります。
自由保育で保育士が気をつける5つのポイント
ここでは、自由保育で働く保育士が押さえるべきポイントについて5つ紹介します。
- 計画立てて保育を実施する
- 必要なときは保育士から声をかける
- 子ども同士のトラブルの仲介をする
- 子どもの行動を予測し安全管理する
- 保護者への報告・連携を密にする
下記では、それぞれのポイントについて解説します。
計画立てて保育を実施する
自由保育は「子ども任せ」ではなく、保育士側には明確なねらいや意図が必要です。個々の成長・発達・興味関心を把握して、子ども一人ひとりに合った援助や環境を設定します。
たとえば、集中力を育てたい子どもには落ち着いて取り組める環境を用意し、協調性を身につけたい子どもには友だちと関わりやすい遊びを提案するなど、具体的な計画に基づいた保育が求められます。
必要なときは保育士から声をかける
自由保育では、状況に応じて保育士から子どもに働きかけることが大切です。
とくに、積極性の低い子どもは、友達作りが苦手で孤立しやすい傾向にあります。保育士から声をかけて周囲との仲を取り持つことで、子どもが孤立せずに楽しく遊べるようになります。
しかし、子どもが一人で遊んでいる場合でも、それが必ずしも悪いことではありません。
子どもが一人遊びに集中しているときは、そっと見守ってあげましょう。
仲間外れのような状況を作らず、クラス全員が楽しく遊べる環境を作ってあげられるかどうか、保育士の手腕が問われます。
子ども同士のトラブルの仲介をする
自由保育は子ども主体の保育なので、子ども同士のコミュニケーションの機会が増えます。
その結果、子ども同士のトラブルが起きやすい環境となります。子ども同士の喧嘩やトラブルは、社会性や人間関係を学ぶ良い機会です。
しかし、どちらかが暴力的な行動をとったり問題が長く続いたりする場合は、保育士が仲介して仲直りのきっかけを与えてあげてください。
仲直りのやり方を教えるのも、保育士の役割です。
子どもの行動を予測し安全管理する
自由保育では、子どもが自由に遊べる時間を多く採用しています。そのため、ときには子どもが予想外の行動をする可能性があります。
保育士は子どもの行動をできるだけ予測し、大きな事故やケガから子ども達を守らなければいけません。
自由保育では子どもの動きが予測しにくいため、保育士には高い安全管理能力が求められます。遊具の配置や環境設定を工夫し、事故やけがを未然に防ぐ配慮が必要です。


保護者への報告・連携を密にする
自由保育では、一斉保育と比べて子ども一人ひとりの活動内容が異なるため、保護者に対してより詳細な報告が必要となります。その日にどのような遊びを選び、どんな成長を見せたかを具体的に伝えましょう。
また、家庭での様子や興味関心についての積極的な情報交換が、園と家庭の連携に繋がります。保護者との信頼関係の構築により、自由保育への理解も得やすくなります。
写真や動画を活用したり、連絡帳に具体的なエピソードを記載したりするなど、子どもの成長が伝わりやすい工夫を心がけることも効果的です。


自由保育に向いている保育士の特徴


自由保育に向いている保育士には、以下のような特徴があります。
- 子どもの意思を尊重できる
- 柔軟性がある
- 臨機応変に動ける
- 子どもの変化を敏感に察知できる
自由保育では、子どもが自主性をもって好きな遊びを安全にできるよう環境を整えることが保育士の役目となります。そのため、子どもの意思を尊重し、一人ひとりのペースに合わせた関わりができる保育士が向いているといえるでしょう。
子どもが「これをやってみたい」と興味を示したときに、否定するのではなく、どうすれば安全に実現できるかを一緒に考えられる柔軟性が求められます。
自由保育では予想外の展開が多いため、臨機応変に動ける能力も欠かせません。計画通りに進まない状況でも動揺せず、その場の状況に応じて最適な判断を下せる保育士が向いていると言えます。
子どもの興味や関心の変化を敏感に察知し、環境設定や声かけのタイミングを調整できる観察力も重要な要素です。
ただし、自由保育と一斉保育に優劣があるわけではありません。やりがいをもって働くためにも、保育士自身の特性や保育観に合った方法を選択しましょう。
自由保育の園への就職・転職をお考えなら「しんぷる保育」にご相談ください



自由保育の園で働きたいけど、どこが自分に合うかわからない…
このように、自由保育の園への就職・転職でお悩みなら『しんぷる保育』にご相談ください。
しんぷる保育は、1都3県(東京・神奈川・千葉・埼玉)を中心に、保育士や保育教諭の就職・転職をサポートする人材紹介会社です。
関東のほぼすべての保育園・認定こども園と取引しているため、豊富な求人の中から、あなたの希望条件に合った自由保育の園を紹介できます。
「子どもの自主性を大切にする保育方針の園で働きたい」
「自由保育で有名な保育園を紹介してほしい」
「給与や福利厚生が充実している園で働きたい」
といったご要望にも、丁寧に対応いたします。
無料で利用できますので、まずは登録してどのような求人があるかチェックしてみてください。
\ たった30秒で登録完了 /
自由保育についてのよくある質問


最後に自由保育に関するよくある質問と回答をまとめます。
自由保育とモンテッソーリ教育はどう違いますか?
自由保育とモンテッソーリ教育は、どちらも子どもの自主性を尊重する保育方法ですが、アプローチ方法や具体的な実践内容には違いがあります。
モンテッソーリ教育は、イタリアの医師マリア・モンテッソーリが考案した教育法で、子どもが自発的に学習に取り組める環境を整えます。
モンテッソーリ教育では、専用の教具を使用する点が特徴的で、感覚教育、日常生活の練習、数教育や言語教育などのさまざまな分野があり、子どもの発達段階に応じて体系的に整備されています。
一方、自由保育では特定の教育法にとらわれず、ままごと道具や絵本、積み木などの、身近な遊び道具や素材を使って子どもが自由に遊べる環境を提供します。
自由保育で子どもがわがままに育つ可能性はありますか?
適切におこなわれる自由保育では、子どもがわがままに育つ心配はありません。自由保育は「何でも許可する」という意味ではなく、保育士がメリハリのある対応をすることが前提です。
危険な行為や他の子どもに迷惑をかける行動については、しっかりと制止し「できないことはできない」と明確に伝えることが大切です。
自由に選択できる範囲と守るべきルールの境界線を明確にすれば、子どもは適切な判断力を身につけられます。
自由保育の園が合わなくて後悔しないか心配です
自由保育の園選びで後悔しないためには、園の保育方針の事前チェックが欠かせません。園の採用HPには「保育方針」や「教育理念」が詳しく書かれていることが多いため、目を通しておきましょう。
また、自分がどのような保育をしたいのかを明確にしておくことも重要になります。
「子どもの自主性を尊重したい」「一人ひとりに寄り添った保育がしたい」など、自分の保育観を整理しておくと、園の方針とのギャップが生じにくくなります。
自由保育の特徴を知ってあなたに合う働き方を見つけよう


自由保育は、子どもの自主性を尊重し、一人ひとりが主体的に遊びを選択できる保育方法です。一斉保育とは異なるアプローチで、子どもの個性や創造性を育てられます。
本記事で紹介した自由保育の特徴やメリット・デメリットを参考に、あなたの保育観に合った働き方を見つけてみてください。
記事を読んで「自由保育の園で働きたい」と思った方で、1都3県の東京・神奈川・千葉・埼玉への就職・転職をお考えなら『しんぷる保育』にご相談ください。
しんぷる保育は関東の転職支援に強く、1都3県のほぼすべての保育園・認定こども園と取引しています。
そのため、豊富な求人データベースから、あなたの希望条件に合った自由保育の園を取りこぼすことなく紹介できます。
無料で相談できますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
\東京・埼玉・神奈川・千葉に転職なら /


